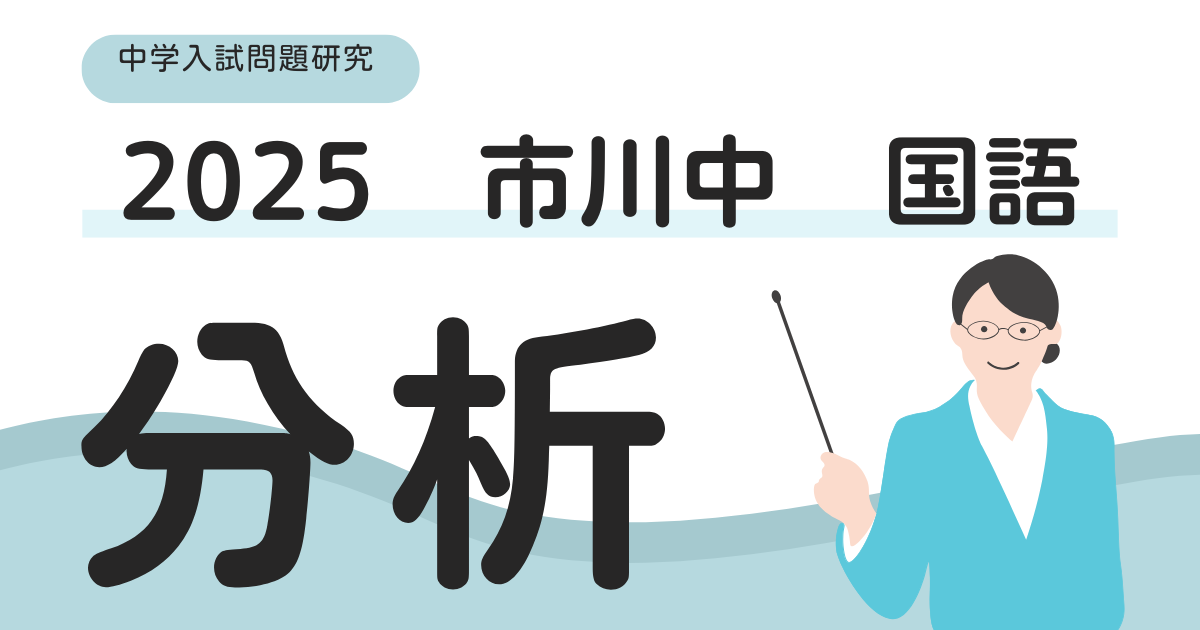
今回は、2025 市川中の国語の問題を見てみましょう。
受験結果
志願者概況
全体 男子 女子
志願者数 2594 1684 910
受験者数 2523 1639 884
欠席者数 71 45 26
合格者数 1085 772 313
教科別平均点
全体 男子 女子
国語(100点) 59.1 57.8 61.4
算数(100点) 55.5 57.6 51.7
社会(100点) 56.3 57.1 54.8
理科(100点) 61.9 64.1 57.6
合計(400点) 232.8 236.7 225.6
合格者得点
全体 男子 女子
合格最高点(4教科合計) 335 335 328
合格最低点(4教科合計) 241 241 241
以上が、学校が公表している2025一般入試の結果です。
全体の倍率は約2.3倍でした。
4科平均点は100点換算で58.2点、国語の平均点は59.1点です。一番平均点が低い算数と理科の差は6.4点でしたので、科目による極端な差はない入試だったといえそうです。
合格者最高点と最低点は、それぞれ100点換算で、84点ー60点です。
平均点より数点上回れば合格できました。
国語解答用紙
まずは解答用紙をご覧ください。

漢字が8問、記号選択が9問、あとは70字、120字、200字の記述が3問です。
この記述が書けなければ得点できません。
ただし、国語においては記述問題はチャンスでもあるのです。
◆みんな苦手・・・受験生は記述問題が苦手です。しかし、多くの学校の記述は難易度はそう高く設定されていません。この学校も標準レベルの記述です。したがって、きちんとセオリーに従って書いておけば、合格点がもらえるのです。そして他の受験生に差をつけることができます。
◆記号選択のほうが厄介・・・国語の記号選択はやっかいです。受験生を惑わせるよう、出題者が知恵を絞ってダミーの選択肢を作るからです。中には、私が見ても「あれ? どっちだ?」と迷う選択肢もあるくらいです。そうした場合は、「この学校のレベルからすれば、これくらいの深読みで十分だろう。他の記号選択の難易度や、例年の出題傾向を考えても、明らかに出題者はこちらの解答を選ばせ、こちらをダミーとして作ったに違いない」と推理して、答えを選びます。時には、明らかにアのほうが正しいと思われる選択肢でも、あえてイを解答とすることもあるくらいです。
しかし、受験生にそうした思考はできません。だからこそ、記号選択のほうが厄介な場合があるのです。
問題文
大問1は、中屋敷均氏の「わからない世界と向き合うために」からの出題でした。
中屋敷氏は、神戸大学大学院農学研究科教授で、植物の細胞機能構造やウィルスの専門家です。
この文章は、専門分野とは関係ない、生きていく上でのアドバイスのようなエッセイです。
専門家の書く文章、とくにエッセイは往々にして読みづらいものが多いのですが、このエッセイは平易な文章ですし、難解な語句も使われていませんので、受験生にとっても読みやすかったと思います。
ただしエッセイですから、主題が途中でシフトしていくのに注意が必要です。
①バンジージャンプ等の世界に伝わる通過儀礼の風習の紹介とその意義
②事故や感染のリスクについての紹介
③リスクを前にした選択の重要性
だいたいこのような流れです。
野蛮に思える通過儀礼の風習も、「恐怖心に打ち勝ち困難なことをやり遂げる」2点において価値があると書いています。
しかし、「自ら選ばない者は、他人に支配される」という言葉を引き、何かを選ぶことから逃げずに、この世界と対峙すること、自分の選択をベストにするよう生きていくことの覚悟を説いています。
わかりやすく含蓄のある論ではあるのですが、前提となる世界各地の通過儀礼の風習が、「個人が自分の意思で選ぶ」ことのできない風習であることが残念です。
私もバヌアツやマサイ族の風習に詳しいわけではないのであくまでも推測にすぎませんが、ナゴール(バンジージャンプ)にしてもライオン狩にしても、同年代の仲間が次々とチャレンジし、命を落とす者もいるのを前にして、「僕はそうした命にかかわる危険な行為はやりません」という道を選択できるはずもないと思うのです。
問5 記述
「その覚悟こそが、『自分の人生を自分のものにする』ということなのだ」とは、どういうことか。本文全体をふまえて120字以内で説明しなさい。
これが記述(1)の問題です。
「その覚悟」の「その」が示すのは、直前の文章全体です。
「リスクを前にして立ちすくみ、何かを選ぶことから逃げ続けていると、誰かに支配されてしまう。・・・それは自らの力でこの世界と対峙することから逃げている行為だからです。絶対に正しい選択など、誰にもできない。私たちにできることは、ベストの選択をすることではなく、自分の選択をベストにするように生きていくことだけです。」
これが直前の文章です。
「その覚悟」=「自分の選択をベストにするように生きていくこと」ということなのでしょう。ただし、「覚悟」というヘビーな語句との相性があまり良くありません。覚悟というからにはもう少し重い内容のはずです。そこでもうすこし視野を広げ、「自らの力でこの世界と対峙すること」と考えるとどうでしょうか。「覚悟」の持つ重みとの相性がよさそうですね。
この記述は、文章全体の内容をまとめる、とくに直前の部分をまとめるだけで正解となるでしょう。
記述(2)
「自分の人生を自分のものにする」には、どのような「覚悟」が必要なのか。本文の内容を参考にしながら、あなたの考えた具体例を200字以内で書きなさい。
「あなたの考えた具体例」がポイントです。
記述(1)ですでに文章の内容をまとめてしまいましたから、その論理の流れにしたがって、何かの具体例を書かなくてはなりません。
ここは素直に、中学受験について書けばよいでしょう。何といっても現在進行形で人生最大の選択を行おうとしているのですから。
大問2は、森田真生「かぞえる」からの出題でした。こちらもエッセーです。
森田氏は、数学者にはくくりにくい活動をしている人です。桐朋中高から東大文2に進学し、社会人経験後、東大理学部数学科に入りなおし、卒業後は執筆活動や講演活動を幅広く行っている、ということのようです。
このエッセイは、自分の幼い息子とのエピソードを紹介しながら、「かぞえる」ことについての雑感を書いたものです。
文章は平易で、こちらも読みにくいものではありません。受験生もすんなり読解できたと思います。
記述も、文章の内容を説明するものでした。
「・・・もちろん彼(1歳半の息子)は、まだ数の概念を理解してはいない・・・息子は、5枚しかないパンケーキを指さしながら、「いち、に、・・・なな!」と自信満々に「数えて」みせた。」
問「数えて」みせたとあるが、ここで筆者はなぜ息子の行動を「 」を用いて「数えて」と表現しているのか。70字以内で説明しなさい。
「」の使われ方を説明する問題です。
「」には、
・強調
・セリフ・会話
・固有名詞
・タイトル
・引用
などの使い方がありますね。
ここでは、「強調」の使われ方ということになるのでしょうけれど、そこに「固有名詞化」のニュアンスも混ざっていますね。
太郎は音痴だが歌が好きだ。家にいるときも、よく声を出さずに歌っている。心の声で歌うとき、太郎は何ともいえない幸福感に包まれる。たとえ音として外に聞こえなくとも、これは太郎にとっては歌うことだった。
ある日、教室の中で太郎は驚いた。隣の席の花子が「歌って」いたからだ。
つまらない短文を作ってみました。
もうおわかりのように、「歌って」と「」に入れた理由は、世間一般で普通に認識されている『歌う』ことと、ここで太郎にとっての「歌う」こととは異なる意味だからですね。
この問題文で、筆者が、「数えて見せた」ではなく「『数えて』みせた」と表記したのには理由があります。それは、一般的に使われる「数える」と、筆者がここで主張している「数える」には違いがあるからです。
筆者は、漢字学の権威である白川静の説を紹介しています。
「かぞへる」は、「か+そへる」と、過ぎ去った日に「か」の音を「そえ」ていくことが由来だそうです。楽しみな日を待ち焦がれながらかぞえる、過ぎ去った日の記憶を半数しながら、姿なき時の流れに一つずつ「か」をそえていく。
ここが理解できれば、この記述は正解に至ることができたでしょう。